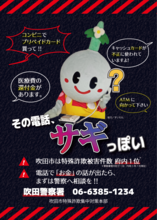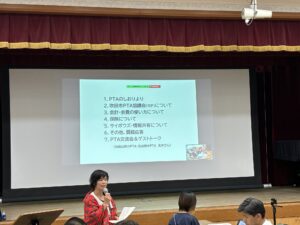/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/DLCOILRXOJO45PYB3F34LZQGEM.jpg)
上の記事は、衆院議院運営委員会の与野党代表者が集い、国会のデジタル化を検討する会合が行われた話です。
特に焦点となったのは、本会議場でのタブレット端末使用の是非。
歴代の正副議長からはタブレット使用に対して一貫して反対の意見が寄せられ、「権威の問題」という理由で本会議場での使用は見送られることに。
しかし、進歩もあり、例えば議員の源泉徴収票の電子交付が可能になるなど、デジタル化に向けた一歩は踏み出されました。
この検討会は、昨年河野太郎デジタル相がスマホを使い注意された事件を契機に始まったもので、多くの政党代表者が参加しています。
高村の考え
この件は前にも取り上げましたが…、改めて。
「権威の問題」とは、一体どんな問題なのでしょうか。
国会がデジタル化の波に乗り遅れている現状に、あきれるばかりです。
歴史ある議会の権威を守るという名目で、技術革新を受け入れない態度は、時代から取り残されるリスクを高めていると言わざるを得ません。しかし、源泉徴収票の電子交付など、デジタル化に向けた歩みを進めている部分もあります。これは、小さな一歩ではありますが、大きな変化への道を切り開く可能性を秘めています。
私たちは、デジタル技術を取り入れることで、より効率的で透明性の高い議会運営が可能になると信じています。
タブレット端末の使用を巡る議論は、ただの始まりに過ぎません。
委員会や小規模な会合でのデジタルツールの使用が徐々に認められれば、本会議での使用も自然と受け入れられる日が来るでしょう。
これは、単にデバイスを使うかどうかの問題ではなく、情報共有の効率化、議論の質の向上、国民への情報提供の透明性向上といった、より大きな価値につながります。
デジタル化を進める上での障壁に対しては、柔軟かつ革新的な思考が求められます。
皮肉にも、デジタル化を推進すべき立場の人物からの反対意見が出ることもありますが、これを乗り越えるためには、世代や立場を超えた共通の理解と目標が必要ですね。